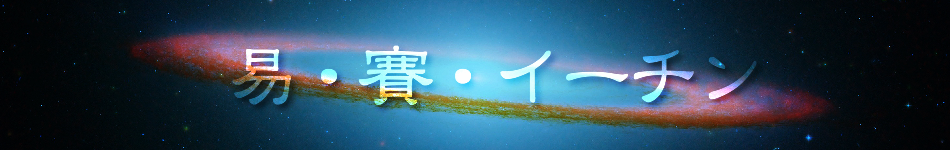易・賽・イーチンカード占いの使者
易・賽・イーチンとは?
易の歴史
古代中国の人々は重要な決断のとき、神に祈るのと同じ態度で易占いにより回答を得てきました。
易経は孔子を含む三人の成人によって完成されたものです。
「易道は深し、人は三聖(伏義・文王・孔子)を更え、世は三古を歴たり」
易経は中国古典の四書五経からまとめられたものですが、日本では、聖徳太子の時代に遣隋使が易経を持ち帰り、平安時代には貴族たちにも広がり、江戸時代にはさらに盛んになります。易占いは武士から知識階層さらには庶民にまで、幅広く活用されてきました。
心理学者ユングは易の大家
フロイトと同時代の精神分析学者ユングは、易の大家としても知られています。
ユングは自身の体験と研究により、易についてこう語っています。
「易があたると、そんなことは偶然だという人がいるが、易にかぎらず、我々は一般に予測できない事態を言い当てると、偶然という言葉を使う。フロイトも言っているように、言い間違いや読み違い、ど忘れなども偶然に起こるわけではない。易が的中するとまぐれだという意見に私は反対である。それどころか、私が体験した易の的中率は偶然の蓋然性をはるかに超えている。易において問題になるのは、偶然性ではなく規則性であることをわたしは確信している。」
易の構成
自然界は「天・沢・火・雷・風・水・山・地」の8つの要素により成り立っています。
卦は陰と陽の組み合わせですべてが表現され、陰陽の3つの組み合わせからなるものが、
八卦といいこれを小成八卦と呼びます。2×2×2=8
八卦と八卦を上下に重ねて構成されるものを大成卦といい64種あります。8×8=64
易占いの色々な方法
- 50本の竹の棒と算木で卦を得る方法…筮竹(ぜいちく)法。
- 8面体のサイコロで卦を得る方法…サイコロ法。
- 6枚のコインの裏表で卦を得る方法…コイン法。
- 64枚のカードで卦を得る方法…イーチンタロット法